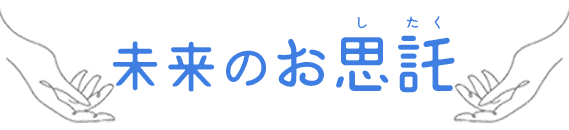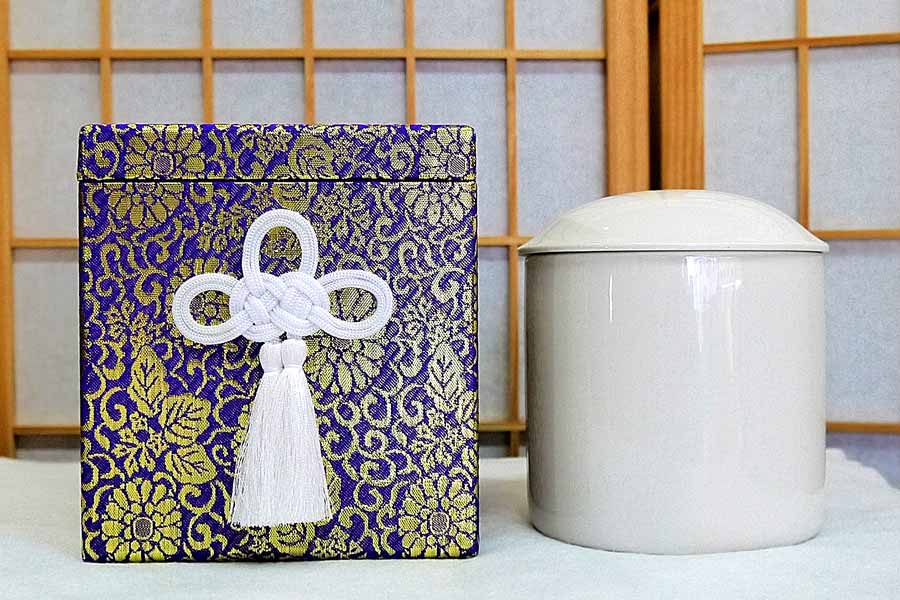大切な故人の遺骨を運ぶときに、どのようなことに注意すればよいでしょうか?
経験することがあまりないので不安に感じる人もいると思います。
運ぶ手段としては、自家用車やタクシーのほか、電車やバス、飛行機などの公共機関を利用することがあるでしょう。
特に公共機関の場合には、何か特別な手続きが必要なのか気になるところですね。また、遺骨を運ぶ方法として宅配便を利用することも、最近では珍しいことではなくなってきました。
それぞれの方法で注意するポイントなどをお伝えします。
遺骨を自分で運ぶ方法
遺骨を運ぶという場面には、どのようなケースがあるのでしょうか?
- 葬儀を終えて自宅へ運ぶケース
- 保管後に自宅から納骨・埋葬するお寺や納骨堂へと運ぶケース
- お寺から自宅へ運ぶケース
- 自宅から散骨場所へ運ぶケース など
様々なパターンが考えられるでしょう。
預かっていた遺骨を返却のために運ぶ場合もあります。国をまたいで運ばなければならないというケースもありえます。
改めて確認してみると意外と多いものですね。
そして、手段としては自家用車やタクシーの利用が主ですが、電車やバス、飛行機や船などの公共機関を利用することもあるということです。
大切な故人の遺骨ですので無事に運べるよう、それぞれ注意するポイントをお伝えしましょう。
運搬時の重さは?

遺骨を運ぶ際、どれくらいの重さを想定したらよいでしょうか?
それは遺骨の量、骨壺・外容器の大きさや材質に左右されますので、次のポイントを参考にしてください。
骨壺の大きさが関東と関西で違うとよく言われていますが、関東では遺骨全部を、関西では一部を納めるという習慣の違いがその理由です。つまり地域によって、収骨をする遺骨の容量が異なるということです。
当然のことですが故人の体格等によっても遺骨の重さは変わってきます。平均的な大人の場合は1kg~3kgと言われています。
骨壺とは遺骨を入れる大切な入れ物です。骨壺の大きさは入れる骨量で異なり、重さは材質によって変わります。
関東では口内経約20cmの7寸壺
関西では口内経約12cmの6寸壺
7寸壺=約3.5kg
6寸壺=約2kg
7寸壺=約6.5kg
6寸壺=約5kg
また、骨箱は骨壺のサイズに合わせて用意されますので、その重さも加わると運搬時には相当な重量になることが想定されます。
遺骨の運び方:自家用車やタクシーを利用する

火葬後は遺族によって収骨が行われ、遺骨を骨壺に納めます。その骨壺は、さらに骨箱に入れられ風呂敷に包まれて渡されることが一般的です。
遺骨の入れ物一式は葬儀社で用意してくれる場合がほとんどです。そして多くの場合、遺骨は遺族によって自宅へと運ばれます。
自家用車やタクシーで運ぶ場合は、トランクではなく喪主が骨箱を抱える形で後部座席に座ります。事情により一人で自家用車を使って、遺骨を運ばなければならないこともあるでしょう。
その場合は、シートベルトなどで骨箱をしっかり固定してください。大切な遺骨ですので、急ブレーキなどで落ちないように万全の対策をとりましょう。

家に運んだ遺骨は、どのように安置したらよいのでしょうか?
仏教式の場合、「後飾り」と呼ばれる祭壇を設置して安置することが一般的です。祭壇の場所は仏壇前や隣、仏壇がなければ部屋の北側か西側がよいと言われています。
遺骨を仏壇の中に納めることはしないので注意してください。「遺影」「位牌」「葬儀の供花」がある場合は一緒に祭壇に置きます。
最近は仏間のある住宅が少なくなりました。その場合には、祭壇の代わりの台を設けるなどして安置します。
骨壺は蓋と本体の間にすき間があり、外気の影響を受けることがあります。長く安置する予定の場合は、特に湿気のある場所を避けた置き場を考えましょう。
保管する期間は四十九日までが一般的ですが、特に決まりがあるわけではありません。後飾りの祭壇も四十九日が過ぎたら片付けますが、そのまま遺影や位牌などを飾る人も多くいらっしゃいます。
自宅で安置することが難しい場合には、事前に一時預かりをしてくれる場所を探しましょう。お寺や納骨堂で預かってくれる場合がありますので、相談するとよいでしょう。
遺骨の運び方:バスや電車を利用する

遺骨をバスや電車で運ぶことは可能です。何らかの手続きをとる必要もありません。
ただし、ほかの乗客に配慮することが必要です。風呂敷や布などで包んで遺骨とはわからないようにしましょう。
今は「骨箱の運搬用バック」があり、葬儀社などから購入することができます。通信販売でも数千円からあるようです。
ショルダー型が持ちやすくておすすめですが、「丈夫な材質か」「運搬物が壊れないような工夫が施されているか」「バックそのものは重くないか」などチェックをしましょう。
また、墓じまい後に自宅で保管せず、すぐに骨壺だけを運びたい場合「骨壺専用バッグ」もあるようです。状況に応じて業者に相談するとよいでしょう。
遺骨の運び方:飛行機や船を利用する

飛行機で遺骨を運ぶ際は、まず各航空会社の約款を確認しましょう。基本的には手荷物として扱われていますが、機内に持ち込める手荷物には制限があります。
例えば、ある航空会社では個数は一人1個までとなっています。サイズは、3辺の合計の和が115㎝以内かつ3辺それぞれの長さ55cm×40cm×25cm以内となっています。
また、安全性確保の観点から座席上の共用収納棚へ置くよう、案内される場合があります。客室乗務員の指示に従ってください。
なお、空港の保安検査場で探知機の反応が出る場合がありますので、「遺骨に関する書類」を携帯することをおすすめします。
また運び方としては、ほかの公共交通機関同様に遺骨とわからないようにするなど、ほかの乗客に配慮しましょう。
遺骨を運ぶのに客船を利用しなければならないという人もいるでしょう。
規制されることはほとんどないと思われますが、念のため、各船会社の運送約款「運送の引受けの章」や、「手回り品の持込み等」を確認しましょう。
持ち込み禁止物としては「臭気を発する物」「爆発物」「遺体」等の項目となっているのがほとんどです。遺骨の記載がないので問題ないようですが、運ぶ際はほかの乗客への配慮を忘れないでください。

まず、死亡届を日本国領事館に提出します。
火葬許可証は、日本の自治体に死亡届が届いてからの発行になりますので、移送時に間に合わないということが往々にしてあります。そのような場合、死亡診断書が火葬許可証の代わりの書類として扱われるとのことです。
なお、死亡届は親族以外でも提出することが可能で、死亡後3ヵ月以内に提出する義務があります。死亡届が受理された後に、死亡の事実が日本の戸籍に反映されます。
戸籍には死亡日時を記載することになっていますので、現地の死亡診断書に日時の記載があるかを必ず確認してから受け取りましょう。

高齢のため重たい遺骨を運べないなど、何らかの理由で遺骨の運搬が難しいという人もいるでしょう。その場合は、搬送を請け負う業者にお願いすることも可能です。
一定期間、場合によっては2~3年といった長期間、遺骨を預かってくれるところもあるようです。遺骨を宅配などで送ることに抵抗がある人、不安がある人はこのようなサービスを利用するのとよいでしょう。
手元にある遺骨を業者に引き渡すときのみ、依頼主と業者間で宅配便を利用することがあります。その際は、業者からキットが送られてきて、説明書に従って梱包し送るだけです。
ほかにも様々なサービスがあるようですので、要望に適した対応をしてくれる業者を探すことをおすすめします。
墓じまい後に永代供養や散骨するという場合、既存のお墓から取り出した遺骨について、洗骨や粉骨が必要になることがあります。
業者が最善の策を提案してくれるので相談してみましょう。いずれにしても、故人の遺骨を大切に扱ってくれる、信頼のおける業者にお願いしたいものです。
遺骨の運び方:宅配便を利用する

様々な理由から自分で遺骨を運ぶことができない人もいるでしょう。その場合には、一般の宅配便で送るという方法もあります。
以前は不適切だと感じる人が多かったかもしれませんが、今はかなり定着してきた手段のようです。
それでは、宅配便を扱う会社での遺骨の扱いをここで確認してみましょう。
引き受け拒絶することがあるものとして「遺骨、位牌、仏壇」とあります。
宅急便、航空搭載とも不可なのものとして「仏像、仏壇、位牌、卒塔婆、遺骨」が挙げられています。
日本郵便のホームページでは、ゆうパックで送ることができないもののリストには「遺骨」は含まれていないことが確認できます。つまり、遺骨の送付を宅配便で行えるのは、日本郵便のゆうパックのみとなります。
ただし、ゆうパックの国際版である「ゆうグローバルエクスプレス」では、「各国共通の禁制品」のリストに「遺体、位牌または遺骨」と載っています。海外へ遺骨を送ることはできないのでご注意ください!

ゆうパックでの送付は、遺骨の入った骨壺を骨箱に入れ、それらをすべて段ボールに入れて送ることになります。それでは、無事に送ることができる梱包例を紹介しましょう。
- 骨箱のサイズに合った段ボール
- 緩衝材(プチプチ、揉んで柔らかくした新聞紙、タオルなど)
- ガムテープ(紙製でなく布製ガムテープか養生テープがよい)
- 骨壺の蓋を固定します。骨壺は蓋のタイプが違いますので、注意しながら遺骨がこぼれないよう固定します。遺骨が少なく、中で激しく動いてしまうことが考えられる場合には、蓋と遺骨の間に綿花などを入れるとよいでしょう。
- 段ボールに骨箱を入れたらすき間に緩衝材を入れましょう。特に桐製の骨箱は割れやすいので搬送中に割れないようにします。
- 骨箱の中に骨壺を入れ、このすき間にも緩衝材を入れて骨壺が動かないようにしましょう。
- 骨箱の上にも緩衝材を入れ段ボールの蓋をしてガムテープで止めます。
- 伝票を書き郵便局の窓口に出します。
品名は必ず記載しなくてはならないので「遺骨」と書きますが、気になるようでしたら「ワレモノ」と書いて送りましょう。
「セトモノ」「こわれもの」「天地無用」のような取扱注意シールは無料ですので、貼付することをおすすめします。
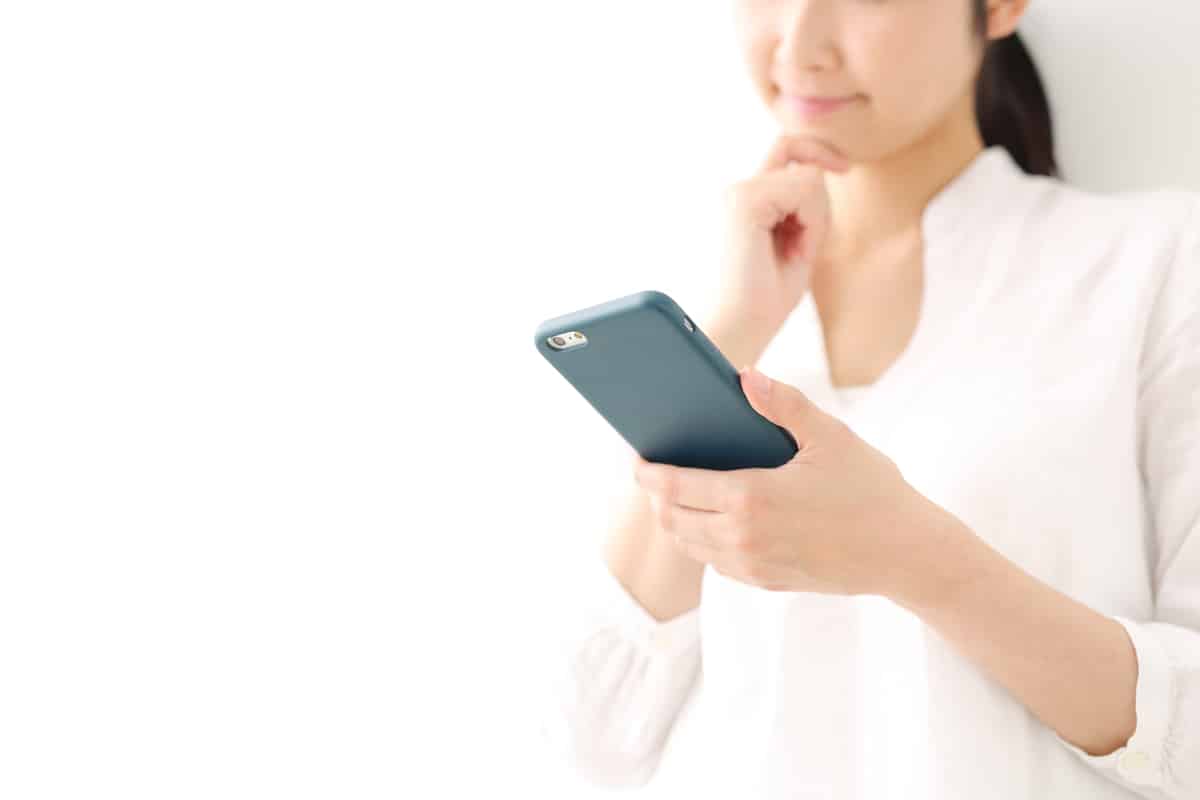
日本の郵便事情は、品質も高く安心できると言われています。それでも配送事故がまったくないわけではありません。
きちんと届くかどうか不安な人は、郵便追跡サービスを利用するとよいでしょう。ホームページ上でゆうパック伝票の右上12桁の数字を入力すると、配送・到着状況を確認することができます。
ゆうパックに係わる損害賠償制度は2通り、ゆうパック単独とゆうパックにセキュリティサービスを付加する方法があります。
荷物を亡失・棄損した場合、ゆうパック単独では30万円を限度とする実損額の賠償です。セキュリティサービスを付加すると限度額50万円の賠償になります。
ただし、損害賠償の対象は骨壺や骨箱等で遺骨自体対象外になります。遺骨は代え難い大切なものですが、その価値をお金で換算できないからです。
なお、宅配便は受け取り拒否ができることになっていますので、事前に先方へ荷物を送る旨の連絡をしておきましょう。
まとめ
初めて遺骨を運ぶという人の参考になりましたら幸いです。
著者情報
 | 未来のお思託編集部 散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。 |